【認知症の症状/心理的理解】
「・・・・・」のなかに入る言葉を答えてください。
最初はわからなくて当然です。
「?」のまま読み流しても大丈夫ですよ。
記事の最後には答えられますから。
スキルアップテスト
1、認知症の中核症状は、記憶障害『・・・・・』、理解力・判断力の障害、失行・失認、性格の変化、の5つに分類される。
2、鏡に自分が映っていても自分と認識できないものを『・・・・』という。
3、心気症状とは、物忘れの訴えや身体の不調を訴える『・・・・・』が特にみられるものをいう。
4、記憶障害のため相手の質問の答えを自分の記憶から引っ張り出せず、その場限りの取り繕った内容を話すものを『・・』という。
5、理解力の低下により、紙や泥、観葉植物など食べ物でない物を口に入れてしまうものを『・・』という。
6、人間が外界の刺激に適応し、円滑な生活が送れるように『・・・・』をはたらかせている。
7、人間の行動は「『・・・・』」「行動」「結果」といった一連の流れで示すことができる。
~解答~
1、見当識障害
2、視覚失認
3、身体的愁訴
4、作話
5、異食
6、自我機能
7、先行条件
解説
1、『見当識障害』
認知症の中核症状は、記憶障害・『 見当識障害 』、理解力・判断力の障害、失行・失認、実行機能障害、の5つに分類される。
認知症には中核症状と周辺症状があるが、周辺症状は必ず発現するとは限らない。
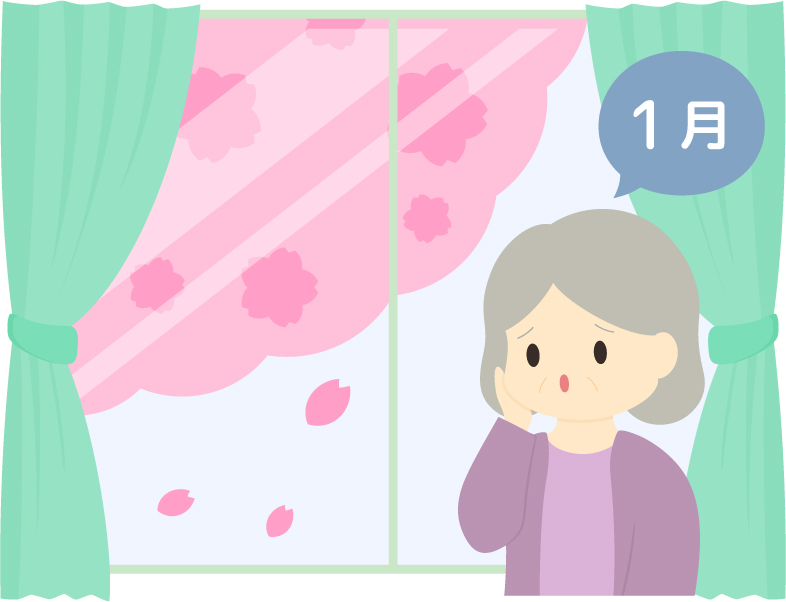
『時間』や『季節感』『場所』や『方向感覚』
自分の置かれている状況を理解する力が低下します。
見当識障害は、時間→場所→人物の順番に進んでいく。
記憶障害
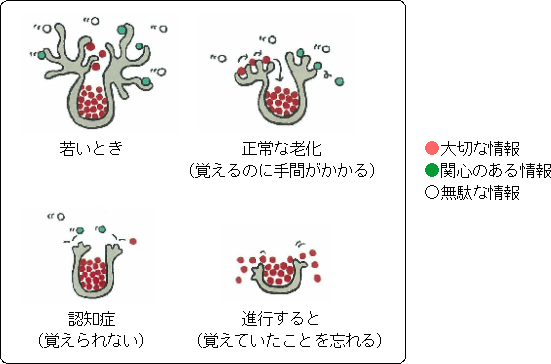
新しいことが憶えられない
記憶が保持できない
「昨日のお昼何食べたっけ?」…物忘れ
「昨日お昼ご飯食べたっけ?」…記憶障害
記憶障害は行動そのものを忘れてしまいます。
理解力・判断力の障害

- 考えるスピードの低下
- 2つ以上の事が重なると同時に行えない。
- 予定以外の出来事に混乱しやすくなる。
- 詐欺被害などの危険
失行

- ある状況のもとで正しい行動ができない。
- 道具を使うことができない
- 服を着ることができない
構成失行
- 図形を描けないなどの症状
観念失行
- 歯ブラシを使うなどの複雑な動作ができない
失認
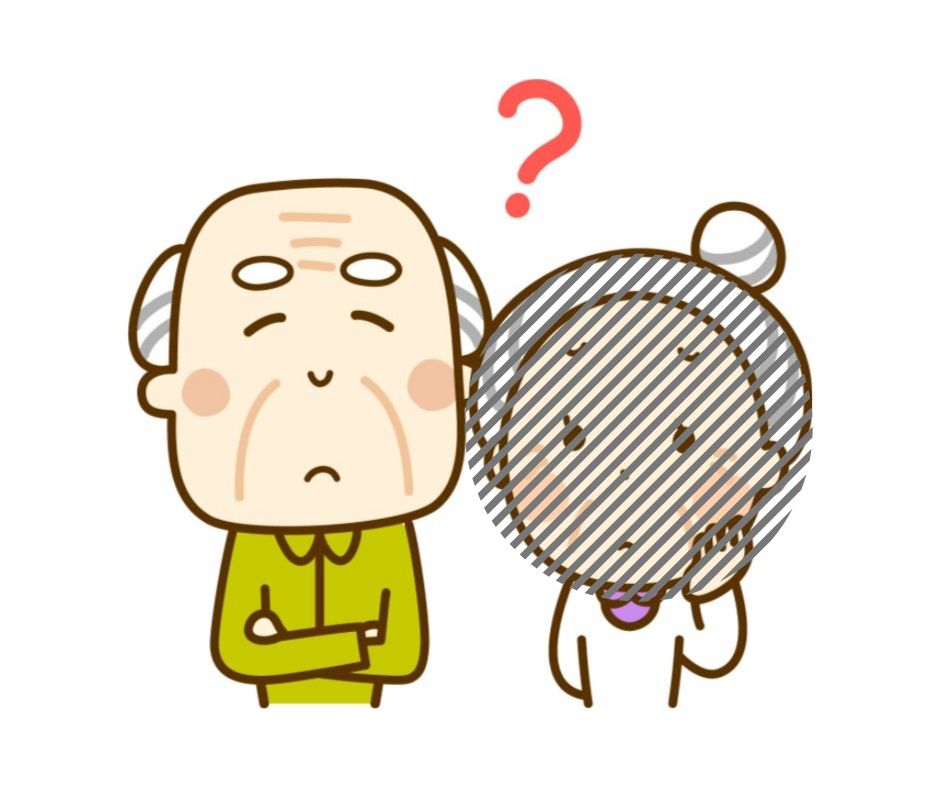
- 身近な物や身体を認識できない
- 知り合いの顔、色、大小などを認識できない
実行機能障害

- 計画的に行動できなくなる
2、『視覚失認』

鏡に自分が映っていても自分と認識できない。
3、『 身体的愁訴 』

物忘れの訴えや身体の不調を訴える。
身体的愁訴が特にみられるものを心気症状という。
4、『作話』(さくわ)
記憶障害のため相手の質問の答えを自分の記憶から引っ張り出せず、その場限りの取り繕った内容を話す。
スポンサーサーチ
・大幅減量ダイエット
・【早い者勝ち!】 あなたのお名前、残ってる?
5、『異食』

理解力の低下により、紙や泥、観葉植物など食べ物でない物を口に入れてしまう。
6、『 自我機能 』
人間が外界の刺激に適応し、円滑な生活が送れるように発揮している心的機能。
7、『 先行条件 』
行動のきっかけとなる目的、行動の直前の環境のこと。
人間の行動は「 先行条件 」「行動」「結果」といった一連の流れで示すことができる。
その他、覚えておきたい認知症のこと
徘徊の背景
本人なりの目的や意味があるが、見当識の障害などから居場所がわからなくなることに起因していると考えられている。
弄便(ろうべん)
便を粘土のように手で弄んだり、壁に塗りつけたりする不潔行為。
高齢者の記憶
認知症高齢者は最近の記憶が障害されやすいため、過去の記憶と現在を混同しやすい。
健忘期
認知症の進行時期のⅠ期は健忘期ともいわれる。
自分が自分でなくなってしまうような慢性的な不快感と恐怖を体験する時期である。
混乱期
認知症の進行時期のⅡ期は混乱期ともいわれる。
今までできたことができなくなったり、記憶にない時間が増えていくことで、焦りや混乱が生じる時期である。
ロールプレイング
ロールプレイングとは、複数の人間が役割を決め、擬似的に現実の場面を創出・体験することで実際の事象に対処できるようにする学習法である。
【グーペ】素敵なお店のホームページを作れます【低コストでホームページ作成】スキルアップテスト再挑戦
再挑戦の前に、改めてまとめておきます。
1、認知症の中核症状は、記憶障害、『見当識障害』、理解力・判断力の障害、失行・失認、性格の変化、の5つに分類される。
2、鏡に自分が映っていても自分と認識できないものを『視覚失認』という。
3、心気症状とは、物忘れの訴えや身体の不調を訴える『身体的愁訴』が特にみられるものをいう。
4、記憶障害のため相手の質問の答えを自分の記憶から引っ張り出せず、その場限りの取り繕った内容を話すものを『作話』という。
5、理解力の低下により、紙や泥、観葉植物など食べ物でない物を口に入れてしまうものを『異食』という。
6、人間が外界の刺激に適応し、円滑な生活が送れるように『自我機能』をはたらかせている。
7、人間の行動は『先行条件』「行動」「結果」といった一連の流れで示すことができる。
改めて、挑戦してみましょう。
1、認知症の中核症状は、記憶障害『・・・・・』、理解力・判断力の障害、失行・失認、性格の変化、の5つに分類される。
2、鏡に自分が映っていても自分と認識できないものを『・・・・』という。
3、心気症状とは、物忘れの訴えや身体の不調を訴える『・・・・・』が特にみられるものをいう。
4、記憶障害のため相手の質問の答えを自分の記憶から引っ張り出せず、その場限りの取り繕った内容を話すものを『・・』という。
5、理解力の低下により、紙や泥、観葉植物など食べ物でない物を口に入れてしまうものを『・・』という。
6、人間が外界の刺激に適応し、円滑な生活が送れるように『・・・・』をはたらかせている。
7、人間の行動は「『・・・・』」「行動」「結果」といった一連の流れで示すことができる。
おまけで、私の好きなニーチェ先生の言葉をご紹介します。
「人間的な善と悪」
悪とは何か。
人をはずかしめることだ。
最も人間的なことは何か。
どんな人にも恥ずかしい思いを
させないことだ。
そして。人が得る自由とは何か。
どんな行為をしても
自分に恥じない状態になることだ。
「悦ばしき知識」
 |
|


One Reply to “介護福祉士国家試験「認知症の理解」スキルアップテスト③ 【認知症の症状/心理的理解】”