覚えるべき2大精神障害 ②
【躁うつ病】についてかんたんにまとめました。
覚えるべき2大精神障害は
①統合失調症
②躁うつ病(気分障害、 双極性感情障害 )
があります。
今回は② 躁うつ病(気分障害、 双極性感情障害 ) についてかんたんにまとめました。
2大精神障害のどちらかは、毎年、出題されているので、必ず押さえましょう。
関連記事
覚えるべき2大精神障害①【統合失調症】介護福祉士国家試験対策「障害の理解」
- 領域:こころとからだのしくみ
- 科目
障害の理解 - 大項目
障害の医学的側面の基礎的知識 - 中項目
精神障害 - 小項目
精神障害の種類と原因と特性
「障害の理解」にだけでなく、「コミュニケーション技術」の科目にも出てきますので、あわせて押さえておきましょう。
また、記事の最後の最後に、うつ病の原因や、治療について、厚生労働省のHPより、 双極性障害について抜粋してまとめています。
試験には細かいところまで出てきませんが、みなさんに知っておいて欲しいと思います。
私自身、過去に「適応障害」というこころの病気になってしまい、うつ症状もあり、ツライ思いをしました。
適応障害はストレスが原因といわれているので、ストレスをためないことで改善されます。
環境を変えることで、一変することもあります。
これは自分の体験からはっきり言えます。
今は環境を変え、いい職場と、いい同僚、いい仲間に出会えて、元気に過ごしています。
以前の職場は、理解しているフリだけで、スタッフの人手不足を理由に、真剣に考えてもらえず、本当にツライ思い出しかありません。
この科目を機に、うつ病について少しでも理解していただけるとうれしいなと思います。
前置き長くなってすみません、解説に行きましょう!
2大精神障害に関する出題
| 第31回 | 統合失調症 | 問題32 問題90 |
| 第30回 | 躁うつ病 | 問題30 |
| 第29回 | 躁うつ病 | 問題89 |
| 第28回 | 躁うつ病( 双極性感情障害 ) | 問題34 |
| 第27回 | 統合失調症 | 問題89 総合問題4 |
| 第26回 | 統合失調症 | 問題95 |
| 第25回 | 躁うつ病 | 問題91 問題97 |
繰り返しますが、見ていただいてお分かりの通り、毎年出題されているので、2大精神障害については、必ず押さえる必要があります。
精神障害の原因
| 精神障害の原因 | ||
| 分類 | 原因 | 具体例 |
| 内因性 | 不明 | ・統合失調症 ・気分障害(躁うつ病) |
| 外因性 | 脳器質・身体 | ・器質性精神障害 (認知症・せん妄) |
| ・症状性精神障害 (身体の病変が脳に影響を与える) | ||
| ・中毒性精神障害 (アルコール・薬物) | ||
| 心因性 | 性格・環境 | ・神経症 ・心因反応 ・パーソナリティ障害 |
躁うつ病に関する出題の傾向
躁うつ病の出題傾向として、特徴を問われるより、躁うつ病の方への対応を聞かれ、主に、うつ状態の方への対応が多いです。
躁うつ病とは
躁うつ病とは、精神疾患の中でも気分障害と分類されている疾患のひとつで、 「躁状態」と、「うつ状態」を交互に繰り返す慢性の病気の事。
昔は「躁うつ病」と呼ばれていましたが、現在では両極端な病状が起こるという意味の「双極性障害」と呼んでいます。
双極性障害
双極性障害は、躁状態の程度によって
「双極I型障害」 と
「双極Ⅱ型障害」
の2種類に分かれます。
介護福祉士国家試験では、分類されての出題はありませんが、知っておいても損はないと思いますので、ちらっとみておきましょう。
「双極Ⅰ型障害」
うつ状態に加え、激しい躁状態が起こる双極性障害。
「双極Ⅱ型障害」
うつ状態に加え、軽い躁状態が起こる双極性障害。
躁状態
特徴
双極Ⅰ型障害の躁状態では、
・気分の高揚
・ほとんど寝ることなく動き回り続ける多動。
・周囲の人に休む間もなくしゃべり続ける多弁。
・法的な問題を引き起こしてしまう。
・失敗の可能性が高いむちゃなことに次々と手を出してしまう。
・他人に干渉する。
・危険な行為などを行うようになる。
軽い躁状態の場合
双極II型障害の軽躁状態は、
- 周囲に迷惑をかけることはない。
- 「ハイだな」というふうに見え、少し行き過ぎという感じがある。
- 気分爽快でいつもより調子がよいと感じている。
- 多くの場合自覚症状がない。
躁状態の方への対応
過去問題を例に見ていきましょう。
介護福祉士国家試験 第28回
コミュニケーション技術
問題34 Gさん(70歳、男性)は、双極性感情障害があり、入退院を何度も繰り返してきた。
最近、様々な考えがつながりもなく浮かんで多弁になる躁状態(そうじょうたい)になり、訪問介護(ホームヘルプサービス)に来たH介護福祉職にも次々に話しかけてきた。
このときのH介護福祉職の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 「一度にいろいろ話すことはやめてください」
2 「また入院することになりますね」
3 「いつもより気分が高ぶっていますよ」
4 「私にはよくわかりませんが…」
5 「もっとお話を聞かせてください」
解答…3
「話しを遮らない」
話しを遮られると、興奮する可能性が高くなる。
「必要以上に話しを引き出さない」
さらに話しを引き出してしまうと、とめられなくなってしまう可能性があります。
「受容的・共感的対応」
否定も肯定もせず、相手の疾患を受け止め、相手にわかるように伝える。
うつ状態

過去問題を例に見ていきましょう。
介護福祉士国家試験 第25回
こころとからだのしくみ
問題 97 Fさん(82歳、女性)は、娘夫婦や孫と暮らしていた。もともと穏やかな性格であったが、1年前に夫を亡くしてからは、ふさぎ込むことが多くなった。半年前に自宅で転倒して大腿骨を骨折した。
それ以来、自立歩行ができなくなり、介護老人福祉施設に入所した。
その後、周囲の人に「死にたい」と、もらすようになった。
Fさんの精神状態として、最も適切なものを 1つ選びなさい。
1 不安神経症(anxietyneurosis)
2 ストレス反応(stressreaction)
3 認知症(dementia)
4 恐怖症(phobia)
5 抑うつ状態(depressive state)
解答…5
中核症状
「抑うつ気分」・ 「興味・喜びの喪失」 を中核症状としていて、これらのうち、すくなくとも1つは現れます。
「抑うつ気分」
何とも形容しがたいうっとうしい気分が一日中、何日も続く。
「 興味・喜びの喪失」
すべてのことにまったく興味をもてなくなり、何をしても楽しいとかうれしいという気分がもてなくなる。
その他の症状
- 早朝覚醒
- 不眠
- 食欲の減退または亢進
- 体重の増減
- 疲れやすい
- やる気が出ない
- 自責感
- 自殺念慮
- 活動性の低下
など、さまざまな症状がある。
中核症状をふくめ5つ以上の症状が
2週間以上毎日続く状態が「うつ状態」です。
うつ状態の方への対応
過去問題を例に見ていきましょう。
介護福祉士国家試験 第30回
コミュニケーション技術
問題 30 抑うつ状態(depressive state)の利用者への介護福祉職の対応として,最も適切なものを 1 つ選びなさい。
1 元気を出すように言う。
2 沈黙している理由を問いただす。
3 会話を促す。
4 気晴らしに散歩に誘う。
5 見守っていることを伝える。
解答…5
介護福祉士国家試験 第29回
障害の理解
問題 89 うつ病(depression)で活動性が低下している利用者への介護福祉職の対応として,適切なものを 1 つ選びなさい。
1 にぎやかな場所に誘う。
2 自殺念慮を打ち明けられても,無関心でいる。
3 訴えに対して,受容的に接する。
4 話が途切れないように,次から次へと話しかける。
5 早く元気になるように,励ます。
解答…3
介護福祉士国家試験 第25回
障害の理解
問題 91 Dさん(42歳、女性)は、専業主婦で小学生の2人の子どもがいる。うつ病(depression)のため、不眠と注意力の低下から家事や育児ができなくなり、精神科病院に通院している。
通院以外は自宅に閉じこもり、横になっていることが多い。訪問した介護職に「子どもの世話ができない自分は母親失格」、「何もできない無能な人間になってしまった」と繰り返し話す。
Dさんへの対応として、最も適切なものを 1つ選びなさい。
1 「ご家族のためにも、早く元気になりましょうね」
2 「気分転換に、旅行に行ったらどうですか」
3 「子どもさんの世話ができないのは、つらいですね」
4 「毎日、洗濯や掃除を頑張りましょう」
5 「いつも同じことを言っていても、病気はよくなりませんよ」
解答…3
負担を増徴させない
・励ましの言葉
・周囲の観念を押し付ける
・否定する
ことは、負担を増徴させる可能性があります。
受容的・共感的に接する
いづれの答えも
・ 見守っていることを伝える。
・ 訴えに対して,受容的に接する。
・ 「子どもさんの世話ができないのは、つらいですね」
受容的・共感的に接しています。
記事の最後に
まとめ自体はかんたんでしたけど、過去問題数が多かったですね。
長くなってすみませんが、それだけ頻出だということ。
絶対に押さえなきゃならないですね。
頻出でいったら、【適応機制】、【発達障害】、【2大精神障害】もほぼ毎年出ているので、おさえておくべきです。
【適応機制】10個の種類。多いけど、意外とかんたん|介護福祉士国家試験対策「こころとからだのしくみ」
【発達障害】は3つだけ覚えてください。介護福祉士国家試験対策「障害の理解」
覚えるべき2大精神障害①【統合失調症】介護福祉士国家試験対策「障害の理解」
介護福祉士国家試験 第30回
コミュニケーション技術
問題 30 抑うつ状態(depressive state)の利用者への介護福祉職の対応として,最も適切なものを 1 つ選びなさい。
1 元気を出すように言う。
2 沈黙している理由を問いただす。
3 会話を促す。
4 気晴らしに散歩に誘う。
5 見守っていることを伝える。
解答…5
介護福祉士国家試験 第29回
障害の理解
問題 89 うつ病(depression)で活動性が低下している利用者への介護福祉職の対応として,適切なものを 1 つ選びなさい。
1 にぎやかな場所に誘う。
2 自殺念慮を打ち明けられても,無関心でいる。
3 訴えに対して,受容的に接する。
4 話が途切れないように,次から次へと話しかける。
5 早く元気になるように,励ます。
解答…3
介護福祉士国家試験 第28回
コミュニケーション技術
問題34 Gさん(70歳、男性)は、双極性感情障害があり、入退院を何度も繰り返してきた。
最近、様々な考えがつながりもなく浮かんで多弁になる躁状態(そうじょうたい)になり、訪問介護(ホームヘルプサービス)に来たH介護福祉職にも次々に話しかけてきた。
このときのH介護福祉職の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 「一度にいろいろ話すことはやめてください」
2 「また入院することになりますね」
3 「いつもより気分が高ぶっていますよ」
4 「私にはよくわかりませんが…」
5 「もっとお話を聞かせてください」
解答…3
介護福祉士国家試験 第25回
障害の理解
問題 91 Dさん(42歳、女性)は、専業主婦で小学生の2人の子どもがいる。うつ病(depression)のため、不眠と注意力の低下から家事や育児ができなくなり、精神科病院に通院している。
通院以外は自宅に閉じこもり、横になっていることが多い。訪問した介護職に「子どもの世話ができない自分は母親失格」、「何もできない無能な人間になってしまった」と繰り返し話す。
Dさんへの対応として、最も適切なものを 1つ選びなさい。
1 「ご家族のためにも、早く元気になりましょうね」
2 「気分転換に、旅行に行ったらどうですか」
3 「子どもさんの世話ができないのは、つらいですね」
4 「毎日、洗濯や掃除を頑張りましょう」
5 「いつも同じことを言っていても、病気はよくなりませんよ」
解答…3
介護福祉士国家試験 第25回
こころとからだのしくみ
問題 97 Fさん(82歳、女性)は、娘夫婦や孫と暮らしていた。もともと穏やかな性格であったが、1年前に夫を亡くしてからは、ふさぎ込むことが多くなった。半年前に自宅で転倒して大腿骨を骨折した。
それ以来、自立歩行ができなくなり、介護老人福祉施設に入所した。
その後、周囲の人に「死にたい」と、もらすようになった。
Fさんの精神状態として、最も適切なものを 1つ選びなさい。
1 不安神経症(anxietyneurosis)
2 ストレス反応(stressreaction)
3 認知症(dementia)
4 恐怖症(phobia)
5 抑うつ状態(depressive state)
解答…5
おすすめテキスト
法改正の部分は正直、独自に調べるのは難しい。
解りやすく、学びやすくしてくれています。
成美堂出版の回し者ではないのですが、本のタイトルで手に取るものが、たまたま成美堂出版の本で、うちには何冊もの成美堂さんがあります。
ずぼらの私には要点まとめとかかかれてしまうと、手に取ってしまいます(笑)
問題集や、過去問、やるときに、びしっとまとまってますし、オールカラーで、まあ、大きいですけど、その分見やすいので、参考書というか、図鑑みたいな感じですね。一冊あると便利です。
1~2年前の中古でも全然いいと思います。
うつ病の参考に
厚生労働省のHPより、 双極性障害について抜粋しまとめます。
試験には細かいところまで出てきませんが、みなさんに知っておいて欲しいと思います。
患者数
日本では、うつ病の頻度は7%くらいで、I型とII型を合わせた双極性障害の人の割合は0.7%くらいといわれています。
そのため、周囲の理解が低く、会社や学校で悩まれる方が多いのではないでしょうか?
原因
双極性障害の原因は、まだ解明されていません。
治療法
薬物療法
気分安定薬と呼ばれる薬が有効だが、強い副作用があります。
双極性障害の治療薬は限られています。
「副作用が出たから、この薬は合わない」とか、「症状が落ち着いた」とやめてしまうと、せっかく回復できる可能性があるのに、これをみすみす失っていることになってしまいます。
医師に報告し、よく相談してください。
心理療法
治療がうまくいくように援助していく、ある種の精神療法が必要です。
再発のきっかけになりやすいストレスを事前に予測し、それに対する対処法などを学ぶことも有効。
規則正しい生活をおくることも、双極性障害の治療にはよい効果があります。
双極性障害から人生を守ることができるのは、自分自身。
自分自身がいかに早く主体的に再発予防に取り組み始めることができるか、それがその後の人生に大きな影響を及ぼすことを知ってください。
再発の予防にいちばん必要なのは、とにかくきちんと薬を飲み続けることです。
何も症状がない時でも、もう大丈夫だと思っても、薬の副作用がつらくても、自己判断で薬を飲むことをやめてしまってはいけません。
薬の副作用が強ければ、これを最小限にする方法を、医師と相談しながら考えていきましょう。
みなさんおつかれさまでした。
いつもお読みいただきありがとうございます。
「障害の理解」頻出問題
覚えるべき2大精神障害①【統合失調症】介護福祉士国家試験対策「障害の理解」
覚えるべき2大精神障害②【躁うつ病】介護福祉士国家試験対策「障害の理解」
4つの【高次脳機能障害】早わかり。介護福祉士国家試験対策「障害の理解」
【発達障害】は3つだけ覚えてください。介護福祉士国家試験対策「障害の理解」
【適応機制】10個の種類。多いけど、意外とかんたん|介護福祉士国家試験対策「こころとからだのしくみ」
関連記事
スポンサーAD

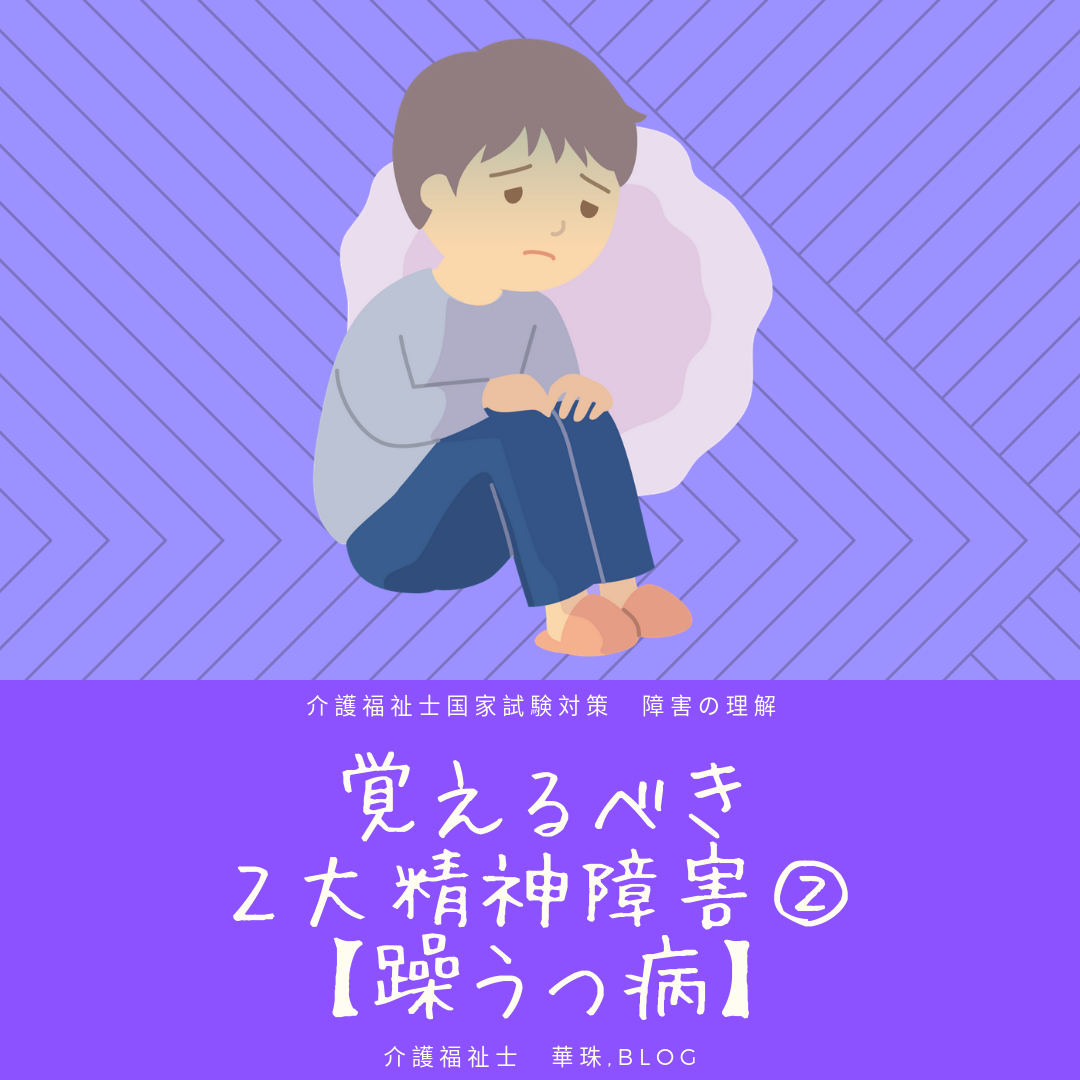
5 Replies to “覚えるべき2大精神障害②【躁うつ病】介護福祉士国家試験対策「障害の理解」”